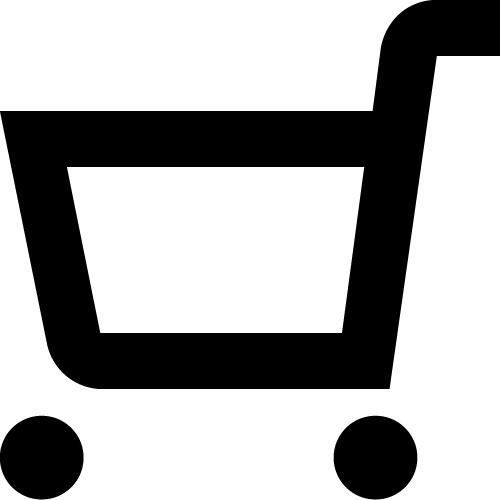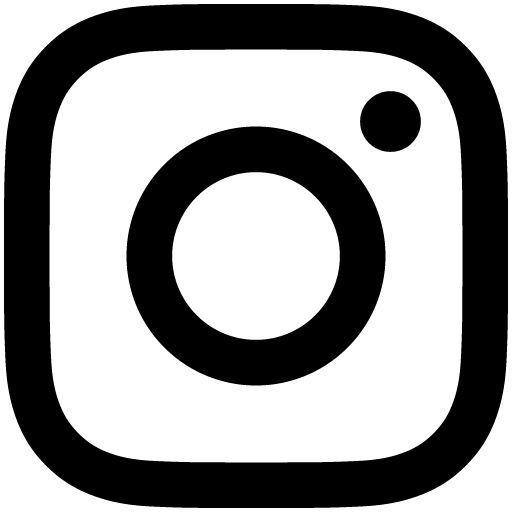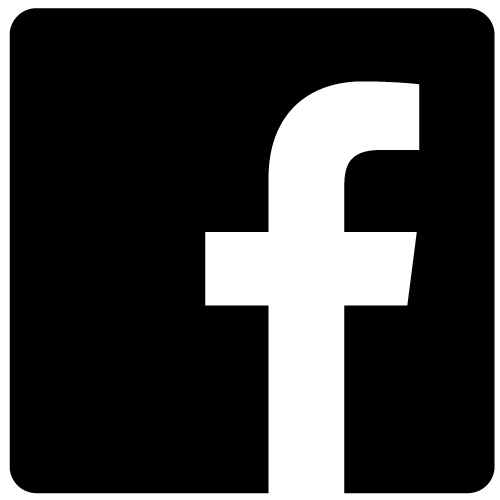年に一回はとどろき酒店に顔を出してくれる福島県南会津郡の会津酒造、渡部景大(わたなべけいた)くん。
景大くんが福岡に来る度に、いつも一緒に楽しく飲んでいますが、飲むばっかりでこれまでちゃんと蔵の話を聞いたことがなかったような…笑
という事で、8月11日にリブランディングした「山の井」の詳細も合わせて色々と話を聞いてきました。

.
.
.
会津酒造は元禄元年(1688年)創業。福島県で2番目に古い蔵です。
当初は味噌や醤油を手がけており、その後現在の蔵の玄関にあたる場所で酒造りを始めました。
酒造りが軌道に乗り、蔵の増設を繰り返していくなかで、味噌・醤油・酒を別々に造ることになったそう。分家して景大くんのご先祖が初代となったのが200年ほど前。景大くんで9代目になります。
戦時中の米不足の時代にも途絶えることなくお酒を仕込み続けてきました。

.
.
.
会津酒造がある南会津郡は、東京都23区と同じくらいの面積。92%が森林で、それ以外はほぼ田んぼ。お米が盛んに作られている地域です。
「出羽燦々」と「五百万石」を掛け合わせて開発された福島県の酒造好適米「夢の香」は、20年以上に渡り南会津郡で作られており、福島県の総生産量の7割を占めています。

.
.
.
景大くんは中学までを地元で過ごし、高校は栃木県宇都宮市、浪人時代を経て大学は東京農業大学へ進学します。
当時蔵で働いていた杜氏さんに跡継ぎがおらず、蔵元杜氏になることを決めた景大くんは、高校3年12月に理系に転身して、東京農業大学を目指しました。
東京農業大学の醸造科を卒業したのち、一旦別の業種を経験したかったそうですが、杜氏さんが体調を崩してしまいあと二年くらいしか居られないという話になったため、急遽そのまま蔵に戻ることになりました。

その後、お父さんと一緒に挨拶へ行ったのをきっかけに、2009年4月から半年間「はせがわ酒店」さんで修行を積み、11月から再び蔵へ戻ります。
2014年からは製造責任者に、2018年には代表取締役に就任しました。
.
.
.
会津酒造の主な銘柄は、地元流通のみの「会津」、特約店向けの「山の井」および「シトラス」。

景大くんが蔵に戻るまでは、会津酒造のお酒は福島県内でしか流通しておらず、ほぼ地元のお酒でした。
それから「飛露喜」の廣木健司さんと、「写楽」の宮森義弘さんに出会って、全国に特約店を広げていけるように。二人に出会えたことが、景大くんにとって大きな転機となったそうです。
「轟木渡さんが福島に来てる時に、宮森さんからお前も一緒にどうだって言って呼んでもらったことが、とどろきさんとの最初の出会いだったりするんです。」と話してくれました。

.
.
.
「山の井」は100年以上前に存在した銘柄を復活させたもの。
「会津」ブランドが地元産米でどれだけ美味しい酒を造れるかを追求してきたのに対し、「山の井」は多様な酒米や菌を試し、試行錯誤を重ねる場でした。
外の意見を聞きながら、色々なお米や、手に入る酵母・麹菌も何百通りという組み合わせを試したそうです。

.
.
.
10年以上、蔵の敷地内地下40mから汲み上げる、全国で二番目に柔らかい超軟水の井戸水と、真冬にはマイナス20度にもなる南会津の厳しい環境に合う菌を探して、多くの経験とデータを蓄積してきました。
そして、長年の試行錯誤を経て、ようやく最も相性の良い菌やレシピを見出し、方向性が定まりました。
新たな山の井として再出発!ということでリブランディングに至ったそうです。
.
.
.
これから軸となる新しい定番酒「清か(さやか)」を中心に、南会津の四季を映す限定酒を2ヶ月ごとに展開していきます。

.
.
「清か(さやか)」は、「超軟水・極寒の地・南会津郡産のお米」という3つの特徴を活かし、南会津を100%表現するお酒。水と氷のように透明感があり、揺るぎない芯を持つ清らかなお酒です。
ラベルは芸術系の大学に通っていたという妹さんによる作品。「水と氷」というお題を出して書いてもらったそうです。
「清かはぬる燗でも美味しいんです(ラベルからみてひやなのかとおもったー byとどろき酒店スタッフ一同)。本当に顔が変わるけど、何でもいけるオールラウンダーですよ。」

.
.
.
追い求めるのはやっぱり「やわらかく、きれいで、飲みやすい酒」。
将来的には、会津酒造のある南会津町永田地区で収穫された酒米だけを使用した酒造りを目指しているようで、「南会津という町が、ボルドーやブルゴーニュのようにみんなに知ってもらえる様な地域にしたいです。」と語ってくれました。
ということで、リブランディングした山の井と景大くんをどうぞよろしくお願いします!!!
.
.
.
山の井のお酒はこちらから