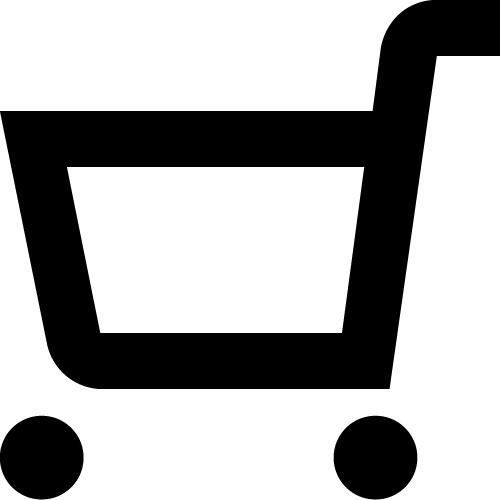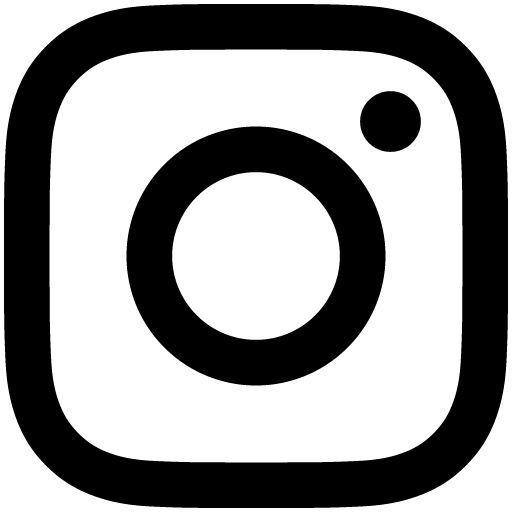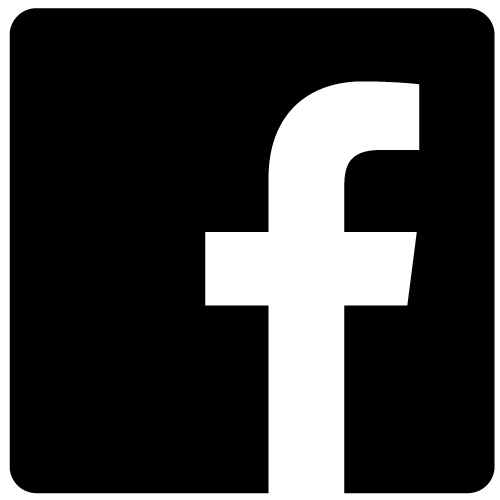とどろき酒店スタッフ、のぶさん&たくま君と一緒に大賀酒造にまたまたお邪魔してきました!
.
.
.
本日の作業の目的は今期のTAMAどっぷりを最高に濁らせること…!!!
新ビンテージのTAMAが入ったタンクから、ひしゃくで醪(もろみ)をすくい、荒めの網でこしながら別のタンクに移していきます。
そうすることでしっかりと濁ったTAMAどっぷりが出来上がるそう。
.
.
.
まずは喜一郎くんとチャギさんがお手本を見せてくれました。

木製のハシゴにのぼってタンクからお酒をひしゃくですくい

荒めの網でこしていきます

網にもろみが溜まったらまた元のTAMAが入っているタンクへ戻します
.
.
この作業を繰り返しながら、TAMAどっぷり用のタンクに350リットルのお酒を移していきます。
どっぷりが注がれるタンクの中には、目盛りの付いた木の棒が設置されており、そこに青いゴムが3箇所巻いてあります。

この一番上のゴムが350リットルの目印。
今日はこの目印までTAMAどっぷりを移し替えない限り帰れません!!!
なかなか大変そうな作業ですが、早速のぶさん&たくま君にバトンタッチ。


TAMAどっぷりがタンクに溜まっていくにつれ、フルーティーで爽やかな香りが漂い始めました。
のぶさんとたくま君が櫂入れ(タンクに入ったもろみを櫂棒で混ぜること)とひしゃくで醪をすくう作業を交代しながら進めていき、ぼちぼち溜まってきたかなーというところで
「じゃ、一旦試飲してみます?」
ということで一時作業を中断して、出来立てのTAMAどっぷりと今期喜一郎くんとチャギさんが造った大賀酒造のお酒たちを試飲させてもらうことになりました。

出来立てのTAMAどっぷりはしっかりと白濁しております

こちらは今期の大賀酒造のお酒たち
.
.
.
まずはもちろん今回の目的TAMAどっぷりから試飲させてもらいました。
試飲にはいつもとどろき酒店のお酒を配達してくれる営業の永江さんも一緒にお手伝いしてくれました。

のぶさん「これまでのTAMAはしっかりした味わいだったけど、よりスッキリした感じになって幅広い料理に合わせやすくなってるかな。焼き鳥が食べたくなるね。鍋との相性も良さそう。水炊きや味噌ベースのもの、もちろんこれまで通りもつ鍋なんか味わいのしっかりしたものとの相性も良さそうだね。」
岡村くん「焼肉のマッコリ的な感じで辛い料理とも相性が良さそうですよね。辛味を和らげてくれるんじゃないかな〜。」
喜一郎くん&チャギさん&永江さん「あー確かに!辛い料理とも相性良さそう!」

と、のぶさん&たくま君の反応のとてもいい感じで、みんなでどんな料理と合わせると良さそうかという話でしばらく盛り上がっていました。
.
.
.
その後、今期の大賀酒造のお酒を一通り試飲させていただき、ひと段落したところで残りの作業に戻ります。

試飲してお酒の話をしたおかげか、何やら和気あいあいとしてきました
.
.
.
のぶさん&たくま君も作業に慣れ、効率が上がってきたのでどんどんTAMAどっぷりが溜まっていきます。
そして作業開始から3時間、目標の350リットルまで到達!👏👏👏
「おー終わりましたねー!」
「案外早く終わりましたねー!」
貴一郎くんとチャギさんは6時間の作業を覚悟していたそうですが、無事に半分の時間で終わらせることができました。
作業開始時点で爽やかでフルーティーな香りがしていましたが、タンクに溜まったTAMAどっぷりはより香りの輪郭もはっきりしてきました。
最後にもう一度TAMAどっぷりを試飲させてもらうと味わいもよりしっかりとしたものになったようです。
.
.
.
なかなか出来ない貴重な体験をさせてもらい、新酒のTAMAどっぷりもとてもいい出来のようです。
喜一郎くんチャギさんありがとうございます!!!

あとは瓶詰め&火入れをしてラベルを貼ったら準備万端!のはずだったんですが…
翌日、営業の永江さんより「もこもこの泡が出てる」と、元気いっぱいのTAMAどっぷりの様子が送られてきました。

この通り予想以上に元気モリモリに活性しているため、ちょっと腰が引けてしまい、ただいま様子見しております。笑
完成までもう少し!
また、出来上がりましたらインスタにてお知らせしようと思っておますので、もう今しばらくお待ちください!!!