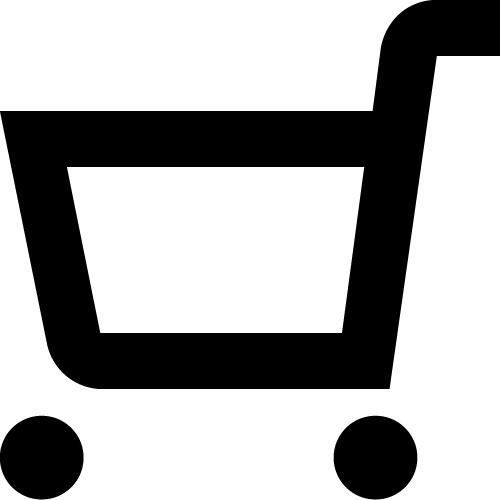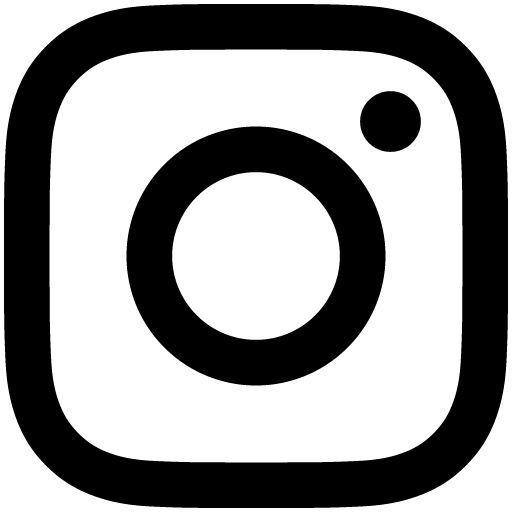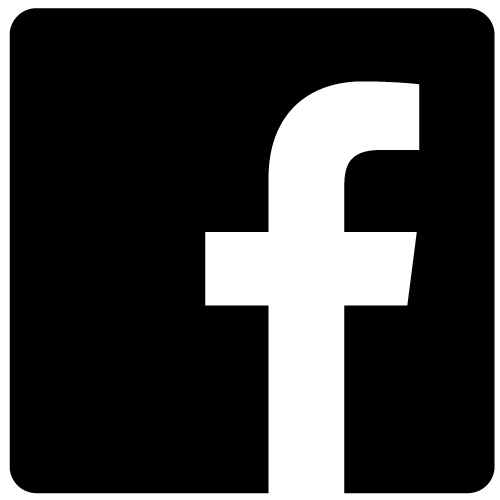こんにちは!
2024年10月にスタッフ皆で焼酎蔵見学ツアーに宮崎に行って参りました!
今年は芋焼酎の山ねこや麦焼酎の中々等多くを手がける『黒木本店』を見学させていただきました。

宮崎駅からバスに乗って40分ほどで黒木本店の看板が見えてきます。
なんとも格好良い門構えです!
蔵では代表の黒木信作さんが迎えて下さいました。
最初に焼酎の歴史やこれから等、笑いも混ぜながらお話をして頂きました。焼酎はもちろん、他の方面にも様々な興味を持ち知識が深い黒木さん。お話がとても面白く、スタッフ一同興味津々で聞き入っていました。

そのお話の中で、『焼酎は香りのお酒であり、その「香り」をどう引き出すかが鍵だ』と仰っていました。
良い原料や麹が良い香りに繋がるということで黒木本店では麹、畑作りから力を入れていることを教えて頂き、その一部を今から見学できるということでわくわく!
最初に向かったのは、黒木本店が原料から良い焼酎を造るべく設立した農業生産法人、「甦る大地の会」の畑と芋の貯蔵をしている倉庫です。
あいにくの雨で畑は遠くからの見学となりましたが、倉庫の中には様々な種類の芋がたくさん!

近年、基腐れ病のせいで黄金千貫の収量が激減している中、自社の畑を持ち一定の収量を確保出来ている点が黒木本店の強みです。
長年自社畑を見ていると、土壌の変化が芋やその先の酒質にも影響を与えるところがおもしろい、と信作さんは語っていました。
尾鈴山蒸溜所が造るウイスキー、「OSUZU MALT」の原料となる麦芽を作る工程のモルティングもここで行われています。

甦る大地の会の畑を後にして次に向かったのは緑あふれる尾鈴山のふもとに設立された尾鈴山蒸留所です
雨が強いため、裏口から入ることになりました。目の前に現れたのは焼酎や麹の原料となる米を蒸す木製の大きな甑(こしき)です。この甑は地元宮崎県産の杉の木から作られています。

次に案内されたのは蒸した米を米麹にするための麹室です。
部屋全体で木のぬくもりを感じる室では、種麹を細かく管理できるように麹箱に仕切りが設けられているのが特徴的です。

そのまま奥に進むと、次に見えるのは醪(もろみ)を発酵させるカメ壺と部屋一面の木桶です。
私たちが訪れたときのカメ壺の中では、代表銘柄「山ねこ」になる予定の醪が元気に発酵していました!

その奥にはズラっと並ぶ木桶達が見えます。
酒蔵に木桶があることは不思議ではないのですが、木桶たちを見て美しいと思ったのは初めて。素敵な空間にうっとり。
大学時代、実家から自社の酒が送ってくるものの、自信をもって振る舞うことはできなかったという信作さん。実家に戻り家業を継いだ後、まずは衛生管理の徹底から始めようと、一番にこの木桶の洗浄をしたそうです。

そんな木桶たちの美しさの余韻に浸りながら歩いていると、見えてきたのはウイスキーやジンを蒸留するためのポットスチルとよばれる蒸留器。

ポットスチルは焼酎であまり使われることはありません。しかし尾鈴山蒸留所とは非常に相性が良く、今では定番銘柄「山ねこ」や「山猿」もこのポットスチルで蒸留した限定酒が存在するほどで切っても切り離せない存在です。
次に見学したのはウイスキー等を熟成させるための樽貯蔵庫です。
ここでは杉や栗、桜など様々な素材で作られた樽が数多く並んでいました。

見学時はスペースにまだ多く空きが見られましたが、これからウイスキーの製造量が増え、樽で空間が埋まっていく様子を想像するだけで圧巻です。
全ての見学を終え黒木本店に戻ると、定番銘柄をはじめとした試飲を用意してくださいました。

まずは「山ねこ 自然発酵」のソーダ割をみんなで乾杯!
カラメルのような甘く香ばしい香りが泡と一緒に心地よくはじけて、試飲ということを忘れてつい「おかわり!」と叫びたくなりました。(上記画像右から2番目)
二杯目は個人的に愛飲している銘柄「山猿 銅釜蒸留」をロックでいただきました。
麦焼酎らしい香ばしさがありながらも、他の麦焼酎では感じられない甘みはまるで生チョコトリュフを食べているかのような感覚です。(上記画像左から5番目)
.
.
.
「百年先の焼酎造りを見据えて」
焼酎という宮崎の土地に根付いた伝統文化を守り、継承していく黒木本店の姿勢。
その姿勢を守りながらも、様々なアイデアを持ってうまれてくる個性的なお酒たち。
そんな黒木本店&尾鈴山蒸留所のお酒を日常のお供にいかがでしょうか?